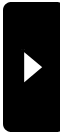2019年10月28日
第3回ケアメン四国in高松 その④
第3回ケアメン四国in高松 その④
第3回ケアメン四国in高松のブログも4回目となりました。
今回から第2部について話しをしていきたいと思います。
第2部では、第1部で話をしていただいた愛媛県以外の四国3県の方に話をしていただきました。
高知県からは奥様を介護されている方、香川県からは母親を介護されている方、徳島県からは介護者支援を行っている方からリレー形式で話して頂きました。各々15分という短い時間で話をして頂き、大変だったと思いますが、ありがとうございました。
前回のブログ内でも少しだけ話しましたが、妻を介護するのと親を介護するのとでは、やはりいろいろと違いがあるようです。妻を介護する場合は、同居が殆どで多くの時間を一緒に過ごしますが、親の介護になると別居している場合も多々あります。

高知県代表として奥様の介護体験を話して下さった方は、『妻の嬉しい時間を増やそう 』を考えながら介護をしていると話されていました。
』を考えながら介護をしていると話されていました。
でも、始めからそういった介護をしていたわけではないそうです。急な物忘れで不安になっている様子やストレスを抱えて円形脱毛症になっている奥様を見て、『今まで、自分は何をしていたんだ。ハグをして、優しく寄り添ってやることが本当は必要だったのに』と振り返って感じてからだそうです。
それからは自分なりに「奥様の嬉しい時間を増やすよう」、奥様に「あなたを大切に思っていますよ」と感じてもらうために、ユマニチュード(認知症ケア法)を自分なりに実践されているそうです。
また、『身体あっての介護ぜよ 』という事で、身体をいたわる事、ストレスを溜めないことに気を使われていると話されていました。80歳になって書道を習いだしたそうで、書道で筆の運びに集中している時には、心が解放されているそうで、やはり人と話をしたり、集中できることをすることが大事と話をして下さいました。
』という事で、身体をいたわる事、ストレスを溜めないことに気を使われていると話されていました。80歳になって書道を習いだしたそうで、書道で筆の運びに集中している時には、心が解放されているそうで、やはり人と話をしたり、集中できることをすることが大事と話をして下さいました。
第1回ケアメン四国in高松から交流している高知県では、高知県須崎市で『さくらの会 ケアメンいごっそう』という会が今年できたそうです。少しずつ、交流の場ができて、少しでも気分が楽になる方が増えればと思います。

今回は、奥様の介護について話をして下さった高知県をクローズアップしました。次回は、母親の介護について話をして下さった香川県にクローズアップしていきたいと思います。
第3回ケアメン四国in高松のブログも4回目となりました。
今回から第2部について話しをしていきたいと思います。
第2部では、第1部で話をしていただいた愛媛県以外の四国3県の方に話をしていただきました。
高知県からは奥様を介護されている方、香川県からは母親を介護されている方、徳島県からは介護者支援を行っている方からリレー形式で話して頂きました。各々15分という短い時間で話をして頂き、大変だったと思いますが、ありがとうございました。
前回のブログ内でも少しだけ話しましたが、妻を介護するのと親を介護するのとでは、やはりいろいろと違いがあるようです。妻を介護する場合は、同居が殆どで多くの時間を一緒に過ごしますが、親の介護になると別居している場合も多々あります。

高知県代表として奥様の介護体験を話して下さった方は、『妻の嬉しい時間を増やそう
 』を考えながら介護をしていると話されていました。
』を考えながら介護をしていると話されていました。でも、始めからそういった介護をしていたわけではないそうです。急な物忘れで不安になっている様子やストレスを抱えて円形脱毛症になっている奥様を見て、『今まで、自分は何をしていたんだ。ハグをして、優しく寄り添ってやることが本当は必要だったのに』と振り返って感じてからだそうです。
それからは自分なりに「奥様の嬉しい時間を増やすよう」、奥様に「あなたを大切に思っていますよ」と感じてもらうために、ユマニチュード(認知症ケア法)を自分なりに実践されているそうです。
また、『身体あっての介護ぜよ
 』という事で、身体をいたわる事、ストレスを溜めないことに気を使われていると話されていました。80歳になって書道を習いだしたそうで、書道で筆の運びに集中している時には、心が解放されているそうで、やはり人と話をしたり、集中できることをすることが大事と話をして下さいました。
』という事で、身体をいたわる事、ストレスを溜めないことに気を使われていると話されていました。80歳になって書道を習いだしたそうで、書道で筆の運びに集中している時には、心が解放されているそうで、やはり人と話をしたり、集中できることをすることが大事と話をして下さいました。第1回ケアメン四国in高松から交流している高知県では、高知県須崎市で『さくらの会 ケアメンいごっそう』という会が今年できたそうです。少しずつ、交流の場ができて、少しでも気分が楽になる方が増えればと思います。

今回は、奥様の介護について話をして下さった高知県をクローズアップしました。次回は、母親の介護について話をして下さった香川県にクローズアップしていきたいと思います。
2019年10月18日
介護の合間 四国の名城巡り⑭
丸亀城その2
整然と積み上げられた石垣の上に毅然とたたずむ亀山城。違った目線での姿も美しい。

この天守の中に一歩踏み入れると、今まで見てきた天守とだいぶ変わっている感じがした。よく考えると、天井が高い。最近のビルでも1階の天井を高くして開放感を出しているが、この城も建坪は小さい割に天井が高いので圧迫感を与えない。2階を吹き抜けにしているような感じである。

通し柱を使わずに各階に柱を立てる構造となっているために階ごとに逓減率は大きくなっている。

最上階になると階段部のスペースを除くと非常に狭い空間となっている。

北窓からは瀬戸大橋の全景が遠くに一望できる。

東窓からは三の丸の向こうに讃岐富士が平地の中にぽつんと立っている。

天守閣を出たころはちょうどお昼過ぎ。本丸の休憩テーブルでコンビニで買ってきたを天守をバックにしてパクり。腹ごしらえをして最後の見どころに出発。

二の丸には大変深い井戸(資料によると深さ65m、標高は60m弱)があり、現在も水を湛えている。

二の丸搦手から石段を下って三の丸に下りる。格好のスペースを見つけ持参したドローンの初仕事。当初から心配していた風が収まらず、おっかな飛ぶには飛んだが風に抵抗して流されないように位置を確保するのに機体が傾き撮影された写真はかなり傾斜している。

風のおさまりを待って再度撮影に挑戦。大手門から見上げる方向からの正面の写真からはこじんまりと整ったシンプルな天守。

周辺の石垣を含めて全体を眺めると最初の写真の如くスマートな若武者を想像する城となる。少し余裕が出来ての自撮り。この撮影場所も高く積み上げられた石垣で築かれた三の丸の曲輪。

動画を添付する技術はいまだ取得できず。その内再度紹介することにする。
見返り坂を下って大手門に到着。城内側の白壁の櫓門が一ノ門、手前の高麗門を二の門(ともに重文)から石垣の上にそびえる天守を仰ぐ。

駐車場に帰る途中で京極家屋敷跡の広場から再度ドローンを飛ばし、高度を上げて天守に近づけようとした。

途中遠距離となり通信不能。どうなるかと心配したが、バッテリー切れの前にゴーホーム無事帰還。丸亀城も無事見学終了となりました。
整然と積み上げられた石垣の上に毅然とたたずむ亀山城。違った目線での姿も美しい。

この天守の中に一歩踏み入れると、今まで見てきた天守とだいぶ変わっている感じがした。よく考えると、天井が高い。最近のビルでも1階の天井を高くして開放感を出しているが、この城も建坪は小さい割に天井が高いので圧迫感を与えない。2階を吹き抜けにしているような感じである。
通し柱を使わずに各階に柱を立てる構造となっているために階ごとに逓減率は大きくなっている。
最上階になると階段部のスペースを除くと非常に狭い空間となっている。
北窓からは瀬戸大橋の全景が遠くに一望できる。
東窓からは三の丸の向こうに讃岐富士が平地の中にぽつんと立っている。
天守閣を出たころはちょうどお昼過ぎ。本丸の休憩テーブルでコンビニで買ってきたを天守をバックにしてパクり。腹ごしらえをして最後の見どころに出発。
二の丸には大変深い井戸(資料によると深さ65m、標高は60m弱)があり、現在も水を湛えている。
二の丸搦手から石段を下って三の丸に下りる。格好のスペースを見つけ持参したドローンの初仕事。当初から心配していた風が収まらず、おっかな飛ぶには飛んだが風に抵抗して流されないように位置を確保するのに機体が傾き撮影された写真はかなり傾斜している。
風のおさまりを待って再度撮影に挑戦。大手門から見上げる方向からの正面の写真からはこじんまりと整ったシンプルな天守。
周辺の石垣を含めて全体を眺めると最初の写真の如くスマートな若武者を想像する城となる。少し余裕が出来ての自撮り。この撮影場所も高く積み上げられた石垣で築かれた三の丸の曲輪。
動画を添付する技術はいまだ取得できず。その内再度紹介することにする。
見返り坂を下って大手門に到着。城内側の白壁の櫓門が一ノ門、手前の高麗門を二の門(ともに重文)から石垣の上にそびえる天守を仰ぐ。
駐車場に帰る途中で京極家屋敷跡の広場から再度ドローンを飛ばし、高度を上げて天守に近づけようとした。
途中遠距離となり通信不能。どうなるかと心配したが、バッテリー切れの前にゴーホーム無事帰還。丸亀城も無事見学終了となりました。
Posted by さぬき男介護友の会 at
17:30
│Comments(0)
2019年10月17日
介護の合間 四国の名城巡り⑬
丸亀城
現存12天守のうち最も小さい天守、でも最も高い石垣の上で凛とそびえている姿は凛々しい若武者の姿(その感想の理由は後ほど)。

東日本に大災害をもたらした台風19号一過。少し風は強かったがさわやかな秋晴れを利用して丸亀城に出かけた。春の花見の時期に立ち寄ったこともあり状況は把握済み。先ずは珍しい城の木図を見たくて資料館に立ち寄ったが、祭日明けの休館であった。

木図とは縮尺1/650の木彫りの模型で、幕府に許可を得るために絵図とともに提出した控えとみられている。

天守と合わせて有名になっている石垣が長雨で崩壊した。現在、基盤の地山の補修を終わり石垣を積み直す作業に移行中の時期と思われる。かなり大きく崩れている。

京極家の屋敷跡をたどって玄関先御門につく。

ここから大手門をパスして一路天守に向かう。直ちに急こう配の坂道が続く。見返り坂と呼ぶ。

このあたりの石垣は20m以上の城壁が続き、隅角部の石垣は算木積みされたきれいな曲線を描き「扇の勾配」と呼ばれている。

さらにもみじに覆われた急な坂道を上ると三の丸に出る。丸亀城の桜も美しかったが、紅葉に覆われた石垣を見るのも楽しみだ。

三の丸は標高50mに位置し、本丸、二の丸をぐるりと一周取り囲む曲輪となっている。東にはなだらかな山なみの讃岐富士が眺められる。

少し上った二の丸は桜の園となっており、夜間ライトアップには丸亀特産のうちわの竹がカバーになっている。

本丸からの天守正面。柱組は1階ごととなっており、全体の安定を考慮して上層ほど狭くなっている。シンプルでスマートなのは1階がかなり高くなっているためで、スマートな若武者の城にたとえた。

以下次号へ。
現存12天守のうち最も小さい天守、でも最も高い石垣の上で凛とそびえている姿は凛々しい若武者の姿(その感想の理由は後ほど)。
東日本に大災害をもたらした台風19号一過。少し風は強かったがさわやかな秋晴れを利用して丸亀城に出かけた。春の花見の時期に立ち寄ったこともあり状況は把握済み。先ずは珍しい城の木図を見たくて資料館に立ち寄ったが、祭日明けの休館であった。
木図とは縮尺1/650の木彫りの模型で、幕府に許可を得るために絵図とともに提出した控えとみられている。

天守と合わせて有名になっている石垣が長雨で崩壊した。現在、基盤の地山の補修を終わり石垣を積み直す作業に移行中の時期と思われる。かなり大きく崩れている。
京極家の屋敷跡をたどって玄関先御門につく。
ここから大手門をパスして一路天守に向かう。直ちに急こう配の坂道が続く。見返り坂と呼ぶ。
このあたりの石垣は20m以上の城壁が続き、隅角部の石垣は算木積みされたきれいな曲線を描き「扇の勾配」と呼ばれている。
さらにもみじに覆われた急な坂道を上ると三の丸に出る。丸亀城の桜も美しかったが、紅葉に覆われた石垣を見るのも楽しみだ。
三の丸は標高50mに位置し、本丸、二の丸をぐるりと一周取り囲む曲輪となっている。東にはなだらかな山なみの讃岐富士が眺められる。
少し上った二の丸は桜の園となっており、夜間ライトアップには丸亀特産のうちわの竹がカバーになっている。
本丸からの天守正面。柱組は1階ごととなっており、全体の安定を考慮して上層ほど狭くなっている。シンプルでスマートなのは1階がかなり高くなっているためで、スマートな若武者の城にたとえた。
以下次号へ。
Posted by さぬき男介護友の会 at
16:20
│Comments(0)
2019年10月16日
第3回ケアメン四国in高松 その3
第3回ケアメン四国in高松 その③です。
今回は、第2部から・・・、と行きたいところですが、振り返る度にお伝えしたいことが出てきて、もう1回だけ第1部の話をさせて頂きたいと思います。
金森様は講演中も、ずっと奥様の手を握っておられました。
若い時は、手をつないでの散歩なんて考えられなかったけども、今では良く手をつないでいるとの事でした。話の最後で、タクティールケアについての話がありました。タクティールケアとは、スウェーデンで生まれたケア方法で、触れることにより、認知症の周辺症状などを和らげる効果があります。

金森様は、最初からタクティールケアを知っていて行っていた訳でなく、奥様に良いと思って行っていたことが、後からいろいろな方と話をする中で、タクティールケアという方法であった事を知ったそうです。その時に「自分のやっていることが間違っていなくて、少し自信につながった。」と話をされていました。
とかく男性介護者は、仕事のように介護をこなす。弱音を吐かないなどと言われ、自分なりの方法で介護をしている方も多いと伺います。介護の仕方で、正解や不正解はないのかもしれませんが、金森さんのようにちょっと自分の介護の仕方を振り返ることも大事なのかもしれません。
第2部では、奥様を介護されている方、母親を介護されている方、介護者支援をされている方の話をリレートークで聞くことができました。
奥様と母親では、また考え方がガラッと変わるかと思います。その辺りの話は、また次のブログで載せさせていただきます。
私は、まだ40歳代ですが、もし自分の奥さんが介護が必要になったら、金森さんのように手をつなごうと思います。手を繋ぐことで、介護者と介護される関係だけでなく、妻と夫に戻れるような気がするからです。
その時に、手を繋いでくれるか心配ですが・・・・
今回は、第2部から・・・、と行きたいところですが、振り返る度にお伝えしたいことが出てきて、もう1回だけ第1部の話をさせて頂きたいと思います。
金森様は講演中も、ずっと奥様の手を握っておられました。
若い時は、手をつないでの散歩なんて考えられなかったけども、今では良く手をつないでいるとの事でした。話の最後で、タクティールケアについての話がありました。タクティールケアとは、スウェーデンで生まれたケア方法で、触れることにより、認知症の周辺症状などを和らげる効果があります。
金森様は、最初からタクティールケアを知っていて行っていた訳でなく、奥様に良いと思って行っていたことが、後からいろいろな方と話をする中で、タクティールケアという方法であった事を知ったそうです。その時に「自分のやっていることが間違っていなくて、少し自信につながった。」と話をされていました。
とかく男性介護者は、仕事のように介護をこなす。弱音を吐かないなどと言われ、自分なりの方法で介護をしている方も多いと伺います。介護の仕方で、正解や不正解はないのかもしれませんが、金森さんのようにちょっと自分の介護の仕方を振り返ることも大事なのかもしれません。
第2部では、奥様を介護されている方、母親を介護されている方、介護者支援をされている方の話をリレートークで聞くことができました。
奥様と母親では、また考え方がガラッと変わるかと思います。その辺りの話は、また次のブログで載せさせていただきます。
私は、まだ40歳代ですが、もし自分の奥さんが介護が必要になったら、金森さんのように手をつなごうと思います。手を繋ぐことで、介護者と介護される関係だけでなく、妻と夫に戻れるような気がするからです。
その時に、手を繋いでくれるか心配ですが・・・・
2019年10月15日
介護の合間 四国の名城巡り⑫
松山城その3
城郭周りの散策を始める。南の紫竹門から侵入する。紫竹門とこれに接続する西塀、東塀で本丸広場方面から攻め入る敵を分断する役目と本丸のからめ手の重要な役割を持つという。それぞれ3つは重文。
写真右上の建物は小天守。その左は南隅櫓。左奥は手前から乾門東続櫓、乾櫓(重文)で二の丸から攻め上ってきた敵を迎え撃つ重要な防御拠点であり、門の左右に櫓が構えられている。

西の乾門方向からの防御態勢はこの図面で明確になる。

中の広場を北に進むと野原櫓(重文)がある。この櫓は本丸の北側を防御する重要な櫓で、日本で唯一現存する望楼型2層櫓で、天守の原型と言われている。

その西側先端に乾櫓(重文)がある。この櫓も2層の隅櫓で築城当初からの建物である。

人通りもなくここで空撮を始める。しかし、アイフォンの画面には空撮禁止の妨害電波が入って?十分な撮影にはならなかったが、感性を働かせて数枚の写真を撮影した。南隅櫓と西隅櫓の間に本丸が少し顔御出している。

乾門と続櫓の防御を強固にするために石垣を築き左右の櫓から攻撃できる構造となっている。

入口から見た乾門と城郭。最も重要な門の一つで堅固な構えになっている。

ここから本丸の城壁に沿って散策する。城壁の上に立っているのは野原櫓である。

市民の散策道となっており歩きやすく整備されていた。天守の鬼門に当たる場所には艮(うしとら)門と続櫓がある。少しの広場を見つけて空撮を開始。本丸内と違ってか妨害電波はなし。動画と一部自撮りを終了。東から見た天守は西側の入り口と同様の構え。右角に天神櫓、左には小天守と虎口の櫓群を控えた天守の姿は壮大。

ちょっと自撮りも。

本日の目標達成してリフトで松山城を下山する。

次回の予定は丸亀城。日取りは未定。
城郭周りの散策を始める。南の紫竹門から侵入する。紫竹門とこれに接続する西塀、東塀で本丸広場方面から攻め入る敵を分断する役目と本丸のからめ手の重要な役割を持つという。それぞれ3つは重文。
写真右上の建物は小天守。その左は南隅櫓。左奥は手前から乾門東続櫓、乾櫓(重文)で二の丸から攻め上ってきた敵を迎え撃つ重要な防御拠点であり、門の左右に櫓が構えられている。
西の乾門方向からの防御態勢はこの図面で明確になる。
中の広場を北に進むと野原櫓(重文)がある。この櫓は本丸の北側を防御する重要な櫓で、日本で唯一現存する望楼型2層櫓で、天守の原型と言われている。
その西側先端に乾櫓(重文)がある。この櫓も2層の隅櫓で築城当初からの建物である。
人通りもなくここで空撮を始める。しかし、アイフォンの画面には空撮禁止の妨害電波が入って?十分な撮影にはならなかったが、感性を働かせて数枚の写真を撮影した。南隅櫓と西隅櫓の間に本丸が少し顔御出している。
乾門と続櫓の防御を強固にするために石垣を築き左右の櫓から攻撃できる構造となっている。
入口から見た乾門と城郭。最も重要な門の一つで堅固な構えになっている。
ここから本丸の城壁に沿って散策する。城壁の上に立っているのは野原櫓である。
市民の散策道となっており歩きやすく整備されていた。天守の鬼門に当たる場所には艮(うしとら)門と続櫓がある。少しの広場を見つけて空撮を開始。本丸内と違ってか妨害電波はなし。動画と一部自撮りを終了。東から見た天守は西側の入り口と同様の構え。右角に天神櫓、左には小天守と虎口の櫓群を控えた天守の姿は壮大。
ちょっと自撮りも。
本日の目標達成してリフトで松山城を下山する。
次回の予定は丸亀城。日取りは未定。
Posted by さぬき男介護友の会 at
23:40
│Comments(0)
2019年10月15日
介護の合間 四国の名城巡り⑪
松山城その2
天守は江戸末期に3層3階地下1階の建物に再興されたことで戦に備えた構造は見当たらず、大きな入母屋破風の非常にシンプルな構造となっている。

小天守2階の窓から見た天守。非常にすっきりした美しいフォルムである。

天守3階の最上階まで急な階段を上ると意外に広い部屋になっている。通常天守の床は板張り、天井板もないが、松山城は各層天井板があり、畳が引ける構造となっている。さらに床の間があり、ふすまを入れるための敷居まである。太平が長く続いた最後の天守建築の特徴を表しているのか。

広く開かれた窓から松山平野を眺望する。南面の本丸広場先には松山市街地が広がる。

小天守を見下ろすとその先にはお濠と二の丸跡が見下ろせる。

西に目をやると、南隅櫓と北隅櫓の間から野原櫓が見えて、その向こうには瀬戸内海と島々が望まれる素晴らしい展望である。
天守を退出するときもう一方の内門がある。

ここを出て仕切門(重文)をくぐり天守を半周すると二の門の前に帰り着く。
来た道を引き返し天守城郭を退出する。
次は天守周辺と本丸周辺をドローンを下げて散策する。次号乞うご期待!
天守は江戸末期に3層3階地下1階の建物に再興されたことで戦に備えた構造は見当たらず、大きな入母屋破風の非常にシンプルな構造となっている。

小天守2階の窓から見た天守。非常にすっきりした美しいフォルムである。
天守3階の最上階まで急な階段を上ると意外に広い部屋になっている。通常天守の床は板張り、天井板もないが、松山城は各層天井板があり、畳が引ける構造となっている。さらに床の間があり、ふすまを入れるための敷居まである。太平が長く続いた最後の天守建築の特徴を表しているのか。
広く開かれた窓から松山平野を眺望する。南面の本丸広場先には松山市街地が広がる。
小天守を見下ろすとその先にはお濠と二の丸跡が見下ろせる。
西に目をやると、南隅櫓と北隅櫓の間から野原櫓が見えて、その向こうには瀬戸内海と島々が望まれる素晴らしい展望である。
天守を退出するときもう一方の内門がある。
ここを出て仕切門(重文)をくぐり天守を半周すると二の門の前に帰り着く。
来た道を引き返し天守城郭を退出する。
次は天守周辺と本丸周辺をドローンを下げて散策する。次号乞うご期待!
Posted by さぬき男介護友の会 at
16:59
│Comments(0)
2019年10月14日
介護の合間 四国の名城巡り⑩
松山城は21棟の重要文化財を持つ四国屈指の名城。あまりにも見るところが多くて、じっくり見たつもりでもまだまだ見残している。桜満開の松山城もよかったが、何度も見にいかなければならない。今回の最高傑作の写真。この景色は地上では見られない。松山城を西から見たもので、南隅櫓(右)・十間廊下・北隅櫓(左)の奥に天守(中央)がそびえている。

昨日は宇和島城から松山城を見るために、肱川上流のなじみの小藪温泉のまったりした湯に浸かって疲れを癒した。近くの鹿野川ダムは放流能力改善のために放水トンネルの大改造が出来ていた。残念ながら昨年の異常豪雨には間に合わなかった。

肱川支川の小田川の河川敷には彼岸花が満開で、こどもの日の凧揚げにはこの辺り大勢の人だかりとなる。

標高132mの勝山に建てられた松山城にはロープウエーで省力化。二の丸からのわが国最大規模の登り石垣を見ながら登りたかったが、次回の楽しみに残した。案内板で今回歩いたルートを整理しておこう。見るところが多いので整理が必要。大手門跡→戸なし門→筒井門・隠門→太鼓門→本丸広場→天守・連立式城郭→紫竹門→野原櫓→乾櫓→乾門を出て城壁の外をめぐって艮(うしとら)門→リフトで下山

まずは大手門跡から正面遠くに天守を望む。城壁の上には太鼓櫓が見える。

折り返しの坂の上には戸無門(重文)

ここを曲がれば城中最も重要で堅固な筒井門。

筒井門右の石垣の裏に隠された隠門と隠門櫓(重文、写真無)。敵の背後を急襲する構え。この城を築城したのは「賤ヶ岳の七本槍」の一人加藤嘉明。築城当時河野氏の本拠地であった湯築城との緊張関係もあったとされていた。太鼓門を通ると広い本丸広場でその奥に姫路城と並ぶ連立式天守が現れる。

入城ゲートを通過していよいよ城内へ。しかし直ちに天守には通じない。城壁の角を曲がると正面に天守が現れる。左が小天守、右が一ノ門南櫓(重文)。
天守は創設当時は5層5階の偉観を誇っていたが、落雷で焼失して江戸末期に3層3階地下1階の天守として復興した。現存12天守の内唯一瓦に「葵の御紋」が付されている。

ここまでたどり着いても容易に天守にはたどり着かない。一の門と櫓で防御する。

続いて二の門と櫓(重文)で再防御。

さらに三の門・櫓(重文)を突破すると目的の天守にたどり着く。
これを人海戦術で突破するとすればどれだけの兵力がいるのだろうか。よくぞ作り上げてものだ。攻め落とすのは兵糧作戦しか考えられない。

これでと思いきや、天守玄関がある中庭を防御する最後の重要な筋鉄門があった。

いよいよ天守に攻め入る。次号要ご期待!
昨日は宇和島城から松山城を見るために、肱川上流のなじみの小藪温泉のまったりした湯に浸かって疲れを癒した。近くの鹿野川ダムは放流能力改善のために放水トンネルの大改造が出来ていた。残念ながら昨年の異常豪雨には間に合わなかった。
肱川支川の小田川の河川敷には彼岸花が満開で、こどもの日の凧揚げにはこの辺り大勢の人だかりとなる。
標高132mの勝山に建てられた松山城にはロープウエーで省力化。二の丸からのわが国最大規模の登り石垣を見ながら登りたかったが、次回の楽しみに残した。案内板で今回歩いたルートを整理しておこう。見るところが多いので整理が必要。大手門跡→戸なし門→筒井門・隠門→太鼓門→本丸広場→天守・連立式城郭→紫竹門→野原櫓→乾櫓→乾門を出て城壁の外をめぐって艮(うしとら)門→リフトで下山
まずは大手門跡から正面遠くに天守を望む。城壁の上には太鼓櫓が見える。
折り返しの坂の上には戸無門(重文)
ここを曲がれば城中最も重要で堅固な筒井門。
筒井門右の石垣の裏に隠された隠門と隠門櫓(重文、写真無)。敵の背後を急襲する構え。この城を築城したのは「賤ヶ岳の七本槍」の一人加藤嘉明。築城当時河野氏の本拠地であった湯築城との緊張関係もあったとされていた。太鼓門を通ると広い本丸広場でその奥に姫路城と並ぶ連立式天守が現れる。
入城ゲートを通過していよいよ城内へ。しかし直ちに天守には通じない。城壁の角を曲がると正面に天守が現れる。左が小天守、右が一ノ門南櫓(重文)。
天守は創設当時は5層5階の偉観を誇っていたが、落雷で焼失して江戸末期に3層3階地下1階の天守として復興した。現存12天守の内唯一瓦に「葵の御紋」が付されている。
ここまでたどり着いても容易に天守にはたどり着かない。一の門と櫓で防御する。
続いて二の門と櫓(重文)で再防御。
さらに三の門・櫓(重文)を突破すると目的の天守にたどり着く。
これを人海戦術で突破するとすればどれだけの兵力がいるのだろうか。よくぞ作り上げてものだ。攻め落とすのは兵糧作戦しか考えられない。
これでと思いきや、天守玄関がある中庭を防御する最後の重要な筋鉄門があった。
いよいよ天守に攻め入る。次号要ご期待!
Posted by さぬき男介護友の会 at
16:28
│Comments(0)
2019年10月12日
介護の合間 ざくろジュース自作
台風19号は幸運にもそれたので、自宅でゆっくりとした時間が持てた。
先日、秋の味覚を友人たちから相次いでいただいた。
一つはアケビ。

まだ少し早い収穫で実が柔らかくなり割れ目ができたころが食べごろ。割れ目に沿って白い綿の所を食べると、何とも言えない優雅な甘さが口の中に広がる。高級和菓子の原材料となる和三盆のようなしっとりとした甘さがこたえられない。しかし、口の中に残る小さな種の処置が面倒だ。

もう一つはザクロ。

これも粒粒を取り出して口に入れるとさわやかな甘さが口の中に広がる。でも一粒一粒種がありこれも食べるのに苦労する。娘にメールを入れるとレシピが紹介された。ざくろジュース。これだと認知症の妻にも味わってもらえると、台風情報を聞きながらぼちぼちと作成。粒粒はきれいに取り出せて水洗いする。取り出した粒をビニール袋に詰めて袋の上からプチプチと指でつぶす。日頃の介護のストレス解消にはうってつけかも?最後に金目のざるで仕上げて器に移す。
きれいな薄ピンク色のざくろジュースの出来上がり。

さわやかな甘さのジュースだがやはり量は少ない。一口で飲むのはもったいないので、飲むヨーグルトで増量して飲んでみたが、ザクロの味も残り大変おいしく健康的なジュースに仕上がった。これならやっちゃんにも飲ませられる。

中東でざくろを食べた方のメールが目に留まった。海外では種ごと食べるらしい。ブドウも同じらしい。食べてみるとあまり違和感は感じられないらしい。一度試してみよう。
台風余波の時間を使っての一コマでした。
先日、秋の味覚を友人たちから相次いでいただいた。
一つはアケビ。
まだ少し早い収穫で実が柔らかくなり割れ目ができたころが食べごろ。割れ目に沿って白い綿の所を食べると、何とも言えない優雅な甘さが口の中に広がる。高級和菓子の原材料となる和三盆のようなしっとりとした甘さがこたえられない。しかし、口の中に残る小さな種の処置が面倒だ。
もう一つはザクロ。
これも粒粒を取り出して口に入れるとさわやかな甘さが口の中に広がる。でも一粒一粒種がありこれも食べるのに苦労する。娘にメールを入れるとレシピが紹介された。ざくろジュース。これだと認知症の妻にも味わってもらえると、台風情報を聞きながらぼちぼちと作成。粒粒はきれいに取り出せて水洗いする。取り出した粒をビニール袋に詰めて袋の上からプチプチと指でつぶす。日頃の介護のストレス解消にはうってつけかも?最後に金目のざるで仕上げて器に移す。
きれいな薄ピンク色のざくろジュースの出来上がり。
さわやかな甘さのジュースだがやはり量は少ない。一口で飲むのはもったいないので、飲むヨーグルトで増量して飲んでみたが、ザクロの味も残り大変おいしく健康的なジュースに仕上がった。これならやっちゃんにも飲ませられる。
中東でざくろを食べた方のメールが目に留まった。海外では種ごと食べるらしい。ブドウも同じらしい。食べてみるとあまり違和感は感じられないらしい。一度試してみよう。
台風余波の時間を使っての一コマでした。
Posted by さぬき男介護友の会 at
14:36
│Comments(0)
2019年10月11日
第3回ケアメン四国in高松 その②
第3回ケアメン四国in高松 その②
前回のブログの続きをアップしていきます。
前回の続きなので、第2部からと行きたいところですが、まだまだ第1部でお伝えしたいところがあるので、引き続き第1部を・・・
ドキュメンタリーの題名『薫ちゃん 認知症の妻へ 1975通のラブレター』は、実際に金森様が介護している中で、つづった妻への思いが元になっています。
実は、金森様は、この妻につづったラブレター以外にも、愛媛新聞に記事『へんろ道』を投稿されていました。今回は、金森様、愛媛新聞様の了解を得て、さぬき男介護友の会と男性介護者と支援者の全国ネットワークで掲載された『へんろ道』の一部を冊子にして、来場して下さった皆様に配らせていただきました。

皆さま、読んでいただけましたか?
介護をしている中で、こんなにもたくさんの思いや気づきを見つけることができるのか とびっくりさせられました。
そんな時に、さぬき男介護友の会の会員さんから「文章を書くと、いろいろなことが整理できるし、集中もできるので良いよ。」との言葉を思い出しました。
何気なく過ぎてゆく日常の中で、その時その時に思う事は、たぶん皆さんたくさんあるのだと思います。
それを振り返って文章にする。それは、記憶の葉っぱが一枚一枚少なくなっていく代わりに、文章としてこれまでの思い出や新たな思い出を残していく『記憶の再編』なのかもしれません。
まだまだ伝えたいことがたくさんありますが、今回はここまでにします。
次回からは、第2部にいけそうかなと思います。
ここでブログを見て下さっている皆様に情報提供を・・・
男性介護者と支援者の全国ネットワークで『男性介護者の介護体験記』をまとめた文集を編集しています。

話すのは、実はけっこうハードルが高いものです。
まずは文章を書いたり読んでみるのも気分転換になるのかもしれません。
前回のブログの続きをアップしていきます。
前回の続きなので、第2部からと行きたいところですが、まだまだ第1部でお伝えしたいところがあるので、引き続き第1部を・・・
ドキュメンタリーの題名『薫ちゃん 認知症の妻へ 1975通のラブレター』は、実際に金森様が介護している中で、つづった妻への思いが元になっています。
実は、金森様は、この妻につづったラブレター以外にも、愛媛新聞に記事『へんろ道』を投稿されていました。今回は、金森様、愛媛新聞様の了解を得て、さぬき男介護友の会と男性介護者と支援者の全国ネットワークで掲載された『へんろ道』の一部を冊子にして、来場して下さった皆様に配らせていただきました。
皆さま、読んでいただけましたか?
介護をしている中で、こんなにもたくさんの思いや気づきを見つけることができるのか とびっくりさせられました。
そんな時に、さぬき男介護友の会の会員さんから「文章を書くと、いろいろなことが整理できるし、集中もできるので良いよ。」との言葉を思い出しました。
何気なく過ぎてゆく日常の中で、その時その時に思う事は、たぶん皆さんたくさんあるのだと思います。
それを振り返って文章にする。それは、記憶の葉っぱが一枚一枚少なくなっていく代わりに、文章としてこれまでの思い出や新たな思い出を残していく『記憶の再編』なのかもしれません。
まだまだ伝えたいことがたくさんありますが、今回はここまでにします。
次回からは、第2部にいけそうかなと思います。
ここでブログを見て下さっている皆様に情報提供を・・・
男性介護者と支援者の全国ネットワークで『男性介護者の介護体験記』をまとめた文集を編集しています。
話すのは、実はけっこうハードルが高いものです。
まずは文章を書いたり読んでみるのも気分転換になるのかもしれません。
2019年10月09日
第3回 ケアメン四国in高松 開催
第3回 ケアメン四国in高松 開催
令和元年10月5日(土)13時30分からサンポートホール高松 54会議室で行いました。
当日は、多くの方にご参加いただき、120名を超える方に来ていただけました。
ご来場して下さった皆様、席が混みあった中での長時間の参加、本当にありがとうございました。

第1部では、金森様ご夫婦のドキュメンタリー映像に続いて、金森様から介護体験について伺う事ができました。奥様を介護していく中での気持ちや病気に対する受け入れなどの移り変わり、気分転換を行うことの大切さなど、来場された皆様も、それぞれにたくさんのことを持ち帰っていただけたと思います。


ドキュメンタリーの中では、記憶のことを木の葉でたとえています。一枚一枚、木の葉が散って行くけども、その散ってしまった葉を探したり、葉っぱが茂っていた時のことを思い出すといった表現がある。
人ぞれぞれ感じ方は違うかもしれませんが、私は、葉が多くても少なくても、病気などで枯れてしまうところができるかもしれないけでも、同じ木であることに変わりはない。自分が愛してきた木を看ていきたいといった金森様の思いを感じることができました。
お伝えしたいことは、まだまだありますが、長くなりそうなので続きはまた次回からアップしていきたいと思います。

令和元年10月5日(土)13時30分からサンポートホール高松 54会議室で行いました。
当日は、多くの方にご参加いただき、120名を超える方に来ていただけました。
ご来場して下さった皆様、席が混みあった中での長時間の参加、本当にありがとうございました。
第1部では、金森様ご夫婦のドキュメンタリー映像に続いて、金森様から介護体験について伺う事ができました。奥様を介護していく中での気持ちや病気に対する受け入れなどの移り変わり、気分転換を行うことの大切さなど、来場された皆様も、それぞれにたくさんのことを持ち帰っていただけたと思います。
ドキュメンタリーの中では、記憶のことを木の葉でたとえています。一枚一枚、木の葉が散って行くけども、その散ってしまった葉を探したり、葉っぱが茂っていた時のことを思い出すといった表現がある。
人ぞれぞれ感じ方は違うかもしれませんが、私は、葉が多くても少なくても、病気などで枯れてしまうところができるかもしれないけでも、同じ木であることに変わりはない。自分が愛してきた木を看ていきたいといった金森様の思いを感じることができました。
お伝えしたいことは、まだまだありますが、長くなりそうなので続きはまた次回からアップしていきたいと思います。